電気工事士(電工)の筆記試験は合格したけど、技能試験ってどうやって勉強すれば良いかわかない方は多いんではないでしょうか。必要な工具や材料ってどこで買うの?全くの素人だけど独学でも合格できるの?合格基準は?複線図が書けないんだけど等々あると思います。
私は電気工事士2種・1種を合格しましたので、その時の経験をもとに勉強法から試験時の注意点を解説します。
記事構成は下記の構成となっています。基礎的な部分を解説していますので、初めて受験をする方でもこの記事をマスターできれば合格することができます。
1.独学で合格はできるのか?
2.事前準備編:対策時期、必要な工具、練習用電材、テキスト、試験の合格基準
3.試験対策編:問題作成時の取り組み手順、複線図の書き方、ケーブルの剝ぎ取り方法、ケーブルの剥き取り長さ、器具への配線接続、失敗したときの裏技、リングスリーブの圧着基準・覚え方
4.よくある失敗例5選(欠陥事例)を紹介
それではどうぞ!!

電工の技能試験は独学でも合格はできるの?
電線も触ったことのないという初めての方は、独学のみでは一発で受かることは難しいかもしれません。
私は工業高校出身の為、技能試験は授業や放課後に電気科の教師指導のもと、各問題を3回程度作成しましたが、一度は不合格となりました(翌年に合格)。練習では1,2回しか不合格にならなかったのですが、本番にナイフで指を切り血が止まらず焦ったのが原因でした。クラスの30人くらい技能試験を受ましたが、一発で合格したのは半数の15人くらいでした。 教師指導の下でも、電線を触ったこともない初めての人たちでは約半数しか受からなかったので、電気工事の経験が無く初めて電線を触るという方は独学で一発合格というのは難しいと思いますが、練習する期間を多くすれば可能だと思います。

独学では難しいとどう取り組めばいいの?
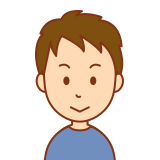
技能試験の対策は、講習を受けましょう。
◎メリット
≪プロの目でチェックしてもらい合格基準であるか判断してもらえる≫
初めて問題の工作物を作ってみると全然手順がわからず、ケーブルの接続方法や 器具の接続方法等欠陥であるかの判断もわかりません。一人で不安状態で練習を繰り返すよりも、プロの目でチェックしてもらい合格基準なのか、ダメな箇所があるのか判断してもらえる
✖デメリット
≪費用が掛かる≫
講習の費用が数万程度掛かります。それ以外にも工具や練習用の電材を購入しないといけないため、出費がキツイ
ただし、資格を取得すれば転職へのメリットや資格手当を貰えるので、未来の自分への投資と思って割り切りましょう
同僚や知り合いに電気工事の資格を持っている方に見てもらえるのであれば独学でも全然ありです。もちろん独学のみでやるっていう方は、練習は2回は繰り返しした方が良いかと思います。
また、電工1種を受験する方は2種とそこまで内容は変わらないので独学でもいけます。私自身も1種は独学で自分で材料を買って練習し合格できました。
事前準備編
対策時期、必要な工具、練習用電材、テキスト試験の合格基準についてみていきましょう。
対策時期
いつ頃から対策をすれば良いかというと、筆記試験後の翌日に解答が出ますので合格点の60点以上だったら、すぐに技能試験の対策準備をしましょう。
技能試験は、筆記試験後の1か月半後くらいに実施される為、あまり時間がありません。筆記試験の合格発表まで待ってから準備だと1か月を切ってしまいます。ですので、筆記試験が合格ラインを超えていたらすぐに取り掛かりましょう。
昨年に落ちてしまった方も、同様に1か月半前から準備するといいです。
必要な工具
工具は自分で用意し、試験の時に持参しなければなりません。
必要な工具ですが、指定工具として下記の6種類があります。※電動の機械は持ち込み不可
①ペンチ ②ドライバ(プラス、マイナス) ③ナイフ ④スケール ⑤ウォータポンププライヤ
⑥リングスリーブ用圧着工具(JIS C 9711:1982・1990・1997 適合品)
指定工具の中にナイフがありますが、ナイフを使用しなくてもワイヤーストリッパーというケーブルを剥くのに便利な専用工具がありますのでそちらがオススメです。これ以外にもラジオペンチ等も持ち込み可能です。
全て揃えるのを面倒くさいなーと思うかもしれませんが、電工の工具セットが販売されています。 圧着工具はリングスリーブ用以外にも種類がたくさんあり、どれを購入してよいか悩みますが、セット販売ですと間違えて購入する心配ないので工具セットを購入するのがおすすめです。
圧着工具だけ無いという方は、 型式:AK-17 を購入していただければ問題無いです。
練習用電材
試験問題は公表されていますので、最低でも1回は練習しましょう。
必要な電材・器具はたくさんあり、ひとつひとつ揃えるとなると揃えるまでに時間を要してしまいます。技能試験の電材一式が販売されていますので、そちらを購入しすぐに練習に取り掛かりましょう。
練習を2回以上やりたいということはケーブルのみも販売しています。また、メルカリ等のオークションに練習用の電材が出品されていることもあるので覗いてみてはいかがでしょうか。
テキスト
講習にせよ、独学でも必ずテキストは用意しましょう。YOUTUBEに解説動画がたくさん上がっていますが、動画だとわかないところも一瞬で過ぎてしまって巻き戻したりと見返すのが面倒です。 テキストであれば、写真と文字で注意点を解説してくれていますのオススメで、該当の年度で公表されている全ての問題が解説されているものを購入するのがオススメです。個人的には会社の後輩に見せてもらった≪すいーっと合格≫というテキストが図解等での説明が丁寧で良かったなと思いました。
試験の合格基準は?
合格基準は、欠陥が1つでもあると不合格になります。
下記リンクに欠陥の判断基準があるので必ず見てください。
handankizyun2017.pdf (shiken.or.jp) :欠陥の判断基準等について
出典:欠陥の判断基準等について | ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター (shiken.or.jp)
たくさん基準があって何を書いてあるのかわからずに不安になりなるとおもうので、ざっくりですが、下記表に簡潔に内容をまとめてみました。※詳細の数値等は記入していませんので注意を!
試験時間内に問題を完成できのはもちろんのこと、器具への接続方法、線の圧着等1つでも欠陥があると一発アウトで不合格で来年にやり直しを食らいます。
2017年度までは重欠陥と軽欠陥と分けられており、欠陥があっても大丈夫でしたが変更となっていますので注意が必要です。他のサイトでは古い制度の情報が載っているところもあるのでご注意を!

試験対策
問題作成時の取り組み手順、複線図の書き方、ケーブルの剝ぎ取り方法、ケーブルの剥き取り長さ、リングスリーブの圧着基準・覚え方、器具への配線接続、失敗したときの対処法について、例題や写真、図、表を用いて解説します。
器具への配線接続については、一般財団法人電気技術者試験センターのHPにて解説されていますので、公式から発表されているので必ず確認してください。ここは、特に注意してもらいたいところや載っていない輪っか作りの方、失敗してしまったときの裏技を解説します。
技能試験の概要と注意すべきポイント (shiken.or.jp) :技能試験の概要と注意すべきポイント
出典:欠陥の判断基準等について | ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター (shiken.or.jp)
問題作成時の取り組み手順(最短で完成させる手順)
初めての方や試験時間内に終わらないって方はどのような手順で作成すれば最短で完成することができるか悩んでいるのではないでしょうか。やはり、技能試験は40分と短い時間なので、いかに効率よくできるかが合格への鍵です。
最短でできる手順は下記の手順となります。
1.問題の条件を確認
2.複線図を書く
3.ケーブルを全て切断
4.配線図通りにケーブル・器具をセットし、外装、絶縁被覆の剥ぎ取り
5.器具に電線を接続
6.電線を同士を接続(リングスリーブで圧着、差込コネクタに挿入)
7.形を整え完成
詳しく説明していきます。手順1~4を15分以内、手順5~6を20分、手順7を2分のイメージをしていただければと思います。メイン作業は手順5~6なので、手順1~4を短縮できればベストです。
1.問題の条件を確認
どこが差込コネクタなのか、リングスリーブなのか等を確認しましょう
2.複線図を書く
複線図がないと完成した時にどう接続したのかわかりにくくなってしまうので必ず書きましょう
3.ケーブルを全て切断
1つ1つケーブルを切って、器具を接続していたら効率が悪いです。この段階で全てのケーブル切断
4.配線図通りにケーブル・器具をセットし、外装、絶縁被覆の剥ぎ取り
器具と接続するケーブルを確認及び違うケーブルで接続することを防止の為、配線図通りにケーブル・器具をセット(ジョイントボックスや金属管には通さなくても大丈夫です)する。
5.器具に電線を接続
やりずらいランプレセプタクル、露出コンセントから取り掛かりましょう
6.電線を同士を接続(リングスリーブで圧着、差込コネクタに挿入)
複線図通りに圧着する電線ごとにまとめて、やり辛いリングスリーブから圧着しましょう。また、電線の本数が多いものからやった方が良いです。
次に差込コネクタで電線同士を接続しましょう。
≪注意点≫
ジョイントボックス、金属管等へケーブルを通すのを忘れずに注意してください。リングスリーブの場合、圧着後に誤りに気付きやり直すと、狭いスぺ-スで配線の剥ぎ取りを行うこととなり、めちゃくちゃ時間ロスとなります。
7.形を整え完成
全ての作業が完成したら、器具の誤配線の確認や寸法を確認し、形を整え完成です。
複線図の書き方
複線図は技能試験で最も重要な部分となります。複線図を誤って書いてしまうと、いくら綺麗に問題を作成できても結線が間違えていると一発アウトです。まずは複線図をマスターしましょう。問題は13問しかないので複線図を暗記するのもありですが、仕事でも使えるので書き方の手順は覚えて損はないです。
1.単線図に書かれている器具、アウトレットボックスを配置通りに書き出す
2.電源の接地側(白線)をスイッチ以外にの器具に接続(線には白又はWと書く)
3.電源の非接地側(黒線)をスイッチ,コンセントへ接続(線には黒又はBと書く)
4.スイッチから対象の器具へ線を接続
5.残りの電線に電線の色を書く
6.電線の接続箇所はリングスリーブを●、差込コネクタを▲と書く
≪実際に公表された問題を例にとって書いてみましょう≫

No7mon.pdf (shiken.or.jp) :2020年度第二種電気工事士 技能試験 問7
出典: ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター
2020年度第二種電気工事士 技能試験 問7を参考に複線図を書いていきます。3路スイッチ、4路スイッチが苦手な方が多いと思うのでこの問題をチョイスしました。
施工条件として、
- VVF用ジョイントボックスAはリングスリーブを使用
- ジョイントボックスBは差込コネクタを使用
- 電源から3路スイッチSまでの非接地側電線は黒色を使用
- …等々あるのでリンク先の問題にて条件を確認してください
書き方手順 ステップ1~6を書いてみると図のようになります





1つ1つ手順通りに書いていけば、複線図を完成させることができます。最初は慣れないですが、練習をしていくうちに徐々に早く書くことができるます。
ケーブルの剝ぎ取り方法
ここでは、電工ナイフを使用する方へケーブルの剝ぎ取りを解説します。ワイヤーストリッパーを使用する方はとばしちゃってください。 失敗しない方法としては、ナイフを切り込む際になるべく浅く・弱く入れることです。深くいれすぎると絶縁被覆に傷がついてしまうためです。

ケーブルの剝ぎ取り長さ
ケーブルの長さは、指定されている長さの±50%以内となっています。これを超えての長さにしてしまうと欠陥となり不合格です。長さは、器具の中心からジョイントボックス
指定された長さにするには、器具への接続やケーブル接続の長さを考慮してケーブルを切らなければなりません。
では、どの程度の長さを考慮すればいいかは、下記の図・表に纏めましたので参考にしてください。

≪公表された問題を例に取って確認してみましょう≫

No7mon.pdf (shiken.or.jp) :2020年度第二種電気工事士 技能試験 問7
出典: ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター
1、支給ケーブル及び対象ケーブル
・VVF2.0mm 2心 250mm 1本 :ケーブル①
・VVF1.6mm 2心 1400mm 1本 :ケーブル④、⑤2本、⑥
・VVF1.6mm 3心 1150mm 1本 :ケーブル②、③、⑦
2、必要なケーブル長さ(剝ぎ取り長さ含め)
長さは、器具中心からジョイントボックス中心までの距離のこと。指定された長さの±50%となっています。
≪150mmケーブル①~⑤ 75mmから225mmが範囲内≫
≪250mmケーブル⑥~⑦ 125mmから375mmが範囲内≫
ケーブル①:電源側の剥ぎ取り不要。150mm+VVFジョイントボックス100mm=250mm
ケーブル②:150mm+VVFジョイントボックス100mm+スイッチ分100mm=350mm
ケーブル③:150mm+VVFジョイントボックス100mm+ジョイントボックス130mm=380mm
ケーブル④:150mm+VVFジョイントボックス100mm+ランプレセプタクル55mm=305mm
ケーブル⑤:150mm+VVFジョイントボックス100mm+スイッチ100mm=350mm ×2本分
ケーブル⑥:器具側の剥ぎ取り不要。250mm+ジョイントボックス130mm=380mm
ケーブル⑦:250mm+ジョイントボックス100mm+スイッチ分100mm=350mm
次に支給されたケーブル長さ以内に収まっているか確認しましょう。
①VVF2.0mm 2心 250mm に対して、必要なケーブル長さは250mm
- ケーブル①の必要な長さ250mm
②VVF1.6mm 2心 1400mm に対して、必要なケーブル長さは1385mm
- ケーブル④ の必要な長さ305mm
- ケーブル⑤の必要な長さ350mm 2本分の為、700mm
- ケーブル⑥の必要な長さ380mm
- 合計:305mm+700mm+380mm =1385mm
③VVF1.6mm 3心 1150mm に対して、必要なケーブル長さは1080mm
- ケーブル② の必要な長さ350mm
- ケーブル③の必要な長さ380mm
- ケーブル⑦の必要な長さ350mm
- 合計:350mm+380mm+350mm =1080mm
支給されたケーブル長さ以内に収まっていますので、各ケーブル長さでケーブルを切断し、ケーブルの剝ぎ取りを行います。
器具への配線接続
ここでは、下記の公式に解説されている中で特に注意して欲しい箇所、記載されていない輪っか作り、外装を剝ぐときに絶縁被覆を傷つけてしまったときの裏技等に解説します。
技能試験の概要と注意すべきポイント (shiken.or.jp) :技能試験の概要と注意すべきポイント
出典:欠陥の判断基準等について | ECEE 一般財団法人電気技術者試験センター (shiken.or.jp)
輪っか作り(ペンチ)
露出コンセント、ランプレセプタクルと配線を接続するときには配線の輪っか作りが必須となります。ただ、初めて作成する方はどういった手順でわからないと思うので手順を紹介します。
1.絶縁被覆を3cm以上を剥ぎ取りする
2. 2~3mmの隙間を開けてペンチで挟む(隙間を開けないと、ビスの被覆噛みの原因になる)
3. ペンチで挟みながら配線を90度曲げる
4.ペンチを挟みながら先端の方を 90度曲げる
5.先端の配線に沿ってペンチにて切断
6.切断した先端をしかっりペンチで挟む
7.ペンチで挟みつつ、左手で配線をペンチの先端利用して反時計周りに回す ※3/4周未満、重ね巻きは欠陥扱いなので注意が必要
8.完成
※6,7手順でペンチでうまくできない方はラジオペンチを利用すると簡単に輪っかを作れます
写真をもとに手順をみていきましょう。
ペンチで輪っかを作るには、練習を繰り返してやらないと上手くいかないです。その場合はラジオペンチを使用すれば簡単に作成することができます。ただし、ラジオペンチの先端で作るとビスがはいらないこともあるの調整し作成してみてください。

ランプレセプタクル
輪っか作り2つ必要、巻きは右方向、ケーブル外装を剥きすぎたりいけない、白線と黒線の極性にも注意等いろいろ気を付けないといけず、結構やっかいな器具です。
手順と主な欠陥事例を下記にあげてみました。

露出コンセント
ランプレセプタクルと同様な手順、欠陥事例となっています。
輪っか作り2つ必要、巻きは右方向、ケーブル外装を剥きすぎたりいけない、白線と黒線の極性にも注意等いろいろ気を付けないといけず、結構やっかいな器具です。

埋込コンセント、スイッチ
器具に心線の長さが書いてあるのでその長さに合わせて心線をカットます。あとは黒線と白線を穴に入れるだけですが、W側に白線を入れてください。

引掛けシーリング
引掛けシーリングは、外装を剥きすぎないことが重要です。外装は2cm剥き、絶縁被覆は1cm程度剥く。器具に心線の長さが書いてあるのでその長さに合わせます。あとは黒線と白線を穴に入れるだけですが、接地側に白線を入れてください。

取付枠
埋込スイッチや埋込スイッチ等を使用する場合に取付枠が必要となります。3つ器具を設置できますが、取付枠に設置する基準は≪器具1個使用の場合は真ん中≫≪器具2個使用の場合は上と下を使用≫≪器具3個使用の全て使用≫

失敗時の対処
①ランプレセプタクル、露出コンセント、引掛けシーリングの外装を剝き過ぎてしまった場合
ランプレセプタクル、露出コンセント、引掛けシーリングの外装を剥きすぎてしまって、基準値よりも絶縁被覆が露出してしまっている場合は、反対側から白・黒線をペンチ軽く握り引っ張ると、電線は動くので露出した分を動かしましょう。コツとしては、線をまっすぐにしないと動きずらいです。

②外装を剥ぎ取りした際に絶縁被覆を傷つけてしまった場合
これは仕事でやると、感電や火災事故の原因、クビになる可能性もありますので絶対にやらないでください。試験のときにどうしても配線が足りずにどうすることもできない場合にやってください。ただし、これをやっとしても不合格になる可能性も十分にあるので自己責任でお願いします。
方法としては、上記の方法と一緒で絶縁被覆に傷がついた場合は反対側から白線・黒線を引っ張り外装の中にいれてしまってください。外装の中に入っていれば、配線を曲げられて状態チェックされても見逃される可能性は大です。
この方法は自己責任でお願いします。責任は絶対に取れませんのでご承知おきください。
リングスリーブの圧着基準
リングスリーブを圧着するときにどの印で圧着すればいいのか良くわからないですよね。 基準を下記表にまとめたので参考にしてください。
覚えるのが面倒という方は下記の通り覚えてみてください。
- 1.6mm 1本を1点、2.0mm 1本を2点と考える
- リングスリーブの種類:4点以下【小】、5点以上【中】
- ダイス:2点【極小】、3~4点【小】、5点以上【中】

よくある失敗(欠陥事例)を紹介
よくある失敗例5つが紹介します。
1.完成していない
2.配線図通りに結線や接続ができていない、器具が配置通りに置かれていない
3.リングスリーブ用圧着工具で適正なサイズやダイスで圧着されていない
4.引掛シーリングの結線で,絶縁被覆が台座の下端から 5mm 以上露出している 露出コンセント、ランプレセプタクルの結線でケーブル外装が台座の中に入っていない
5.ランプレセプタクル又は露出形コンセント等の輪っかの巻き付けやカバーがしまらないくらい絶縁被覆がながい
この記事では、よくある失敗例の対策を記載されていますので該当の見出しをみてみてください。


